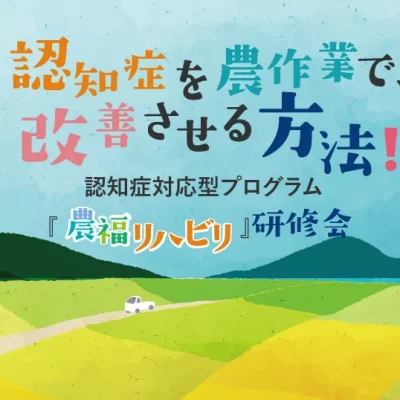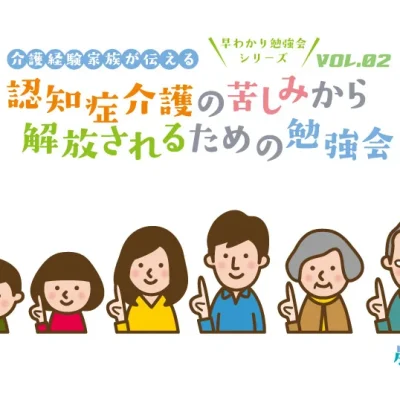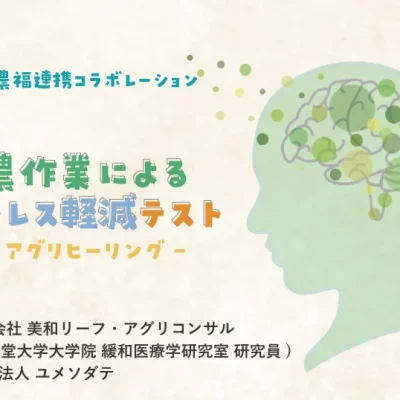農福連携とは、どのような取り組みなのか。
実践でもっとも大切なこと、重要なこととは何か。
そして、誰のために、何のために実施するのか。
私たちは、私たちの実践する「農福連携」の目的を明らかにして活動しています。
農福連携とは何か
農福連携とは、「農業」と「福祉」が、産業分野・業種を越えて、社会課題解決のために連携する取り組みのことです。
農福連携のメリット
農業と福祉の親和性は高く、以前からこれらを組み合わせた取り組みは行われてきました。
近年、社会的に立場の弱い人達の個性を活かす活躍の場所として広がりはじめています。

現在では、農業の担い手不足解消や障害者の雇用促進にとどまらず、様々な背景を持つ方々を対象にした農福連携が行われています。
ひきこもりや認知症高齢者、発達障害の子どもたち、アルコール依存症など、農業の持つ機能や効果を活用し、農と福祉の融合は、様々な効果から多様な広がりをみせています。
農福連携が必要とされる背景
人口減少、超高齢社会を迎え、社会には様々な課題が山積しています。
こうした課題は、これまでの延長線上の制度・政策ではうまく解決できないことが多く、既存のモデル構造から脱却したイノベーティブな取り組みが必要とされています。

地域社会の“困りごと”と“困りごと”を掛け合わせ、相互に解決してゆく。
農福連携は、このような考え方で、広がり始めた取り組みのひとつです。
そして現在、農業と様々な“困りごと”を掛け合わせ、更に拡張した新たな農福連携の取り組みが生まれてきました。
農林水産省の示す農福連携の定義と方針
農林水産省では、農福連携の取り組み方針と目指すべき方向として、次のように説明しています。
農林水産省が定める定義
農福連携とは、障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組です。 農福連携に取り組むことで、障害者等の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながる可能性もあります。
引用元:農福連携の推進:農林水産省
農林水産省が定める取組方針と方向性
また、農林水産省 農村振興局 都市農村交流課による「農福連携をめぐる情勢」の資料では、以下の説明がされています。
農福連携は、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組です。また、全ての人々が地域で暮らし、多様な形で社会に参画し、その生きる力や可能性を最大限に発揮できる地域共生社会の実現に資する取組です。
『農福連携等推進ビジョン』に基づきまして、地域で広げる、未来に広げる、絆を広げる、を新たなスローガンとして、政府一体となって、厚生労働省、農林水産省が中心となり、法務省、文部科学省と共に、農福連携を一層推進してまいります。
引用元:農福連携をめぐる情勢:農林水産省
対象者は、高齢者、生活困窮者、ひきこもりの状態にある者の就労・社会参画支援や、犯罪をした者等の立ち直り支援にも拡大。 そして、農業・農村における課題、福祉(障がい者等)における課題を相互に解決してゆく取り組み、としています。
様々な種類の作物が生産・加工・販売され、多様な作業が必要となる農業現場では、個々の特性に合った作業との出会いによって、障害者等も農業の貴重な働き手となるとともに、工賃の向上等を通じた生活の質の向上も実現できうる、としています。
また、福祉サイドは、これまでの限定的な仕事の発想から脱却し、新たな活躍の場所で、さまざまな作業を行い就労とともに工賃上昇と社会参画の意識による自立の支援をおこなう。
農業の活用により、相互の課題解決とともに、それぞれのメリットを享受できるような取り組みと定義しています。
農福連携の評価軸とは
農福連携の定義は、推進する事業体や各地域の課題によって異なり、すべての農福連携活動を網羅して表現することは困難といえます。
敢えて、一言に凝縮するとするならば、 「農業と福祉による、相互の課題解決のための取り組み」と言えるでしょう。

しかし、農業側と福祉側の設定した指標の達成で、成功と評価されるのでしょうか?。
農作業の効率化や農業経営の拡大、賃金向上を前提とした生きがいの創出という評価軸では、その本質から遠ざかってしまうのではないでしょうか。
最も重要なのは、当事者とその家族が抱える本質的な課題が解決されているのか、ということ。
本当に、当事者自らが人生を選択し、そのひとらしく生きて行くための発見や創造に繋がっているのか、それが私の実践する農福連携の本質であると考えます。
農福連携の主体者と本来の目的
農福連携の本当の主体は誰なのか? そして、農福連携の本来の目的は何なのか?

私が考える農福連携とは、 「社会的に立場が弱い人が、農業分野において、自らの存在と能力を肯定する経験を得て、本人がのぞむ人生を送るためのきっかけとなる取り組みである」と定義しています。
つまり、主体は、当事者とその家族であること、 支援ではなく、共生のための取り組みであること。
私たちは、社会全体の幸福を包摂するための取り組みを実践し、ひとりひとりが望む人生を生きながら共生できる世界を目指します。